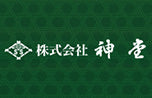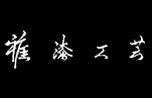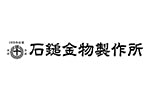初めての梅干し作り。ドキドキしながら漬けてみました!
こんにちは。今年、人生で初めて「梅干し作り」に挑戦しました。 最初は「難しそう」「カビちゃいそう」と不安もありましたが、 実際にやってみると、意外とシンプル! ゆっくりじっくり梅が変化していく様子にワクワクしました。
この記事では、初心者の私が実際に作ってみた梅干しの作り方を、 「これから作ってみたいな」という方に向けてご紹介します!
材料と道具(私が使ったもの)
・完熟梅(南高梅)…2kg
・粗塩(塩分15%)…300g
・食品用のアルコール製剤(消毒用)…適量
・保存容器(ガラス瓶)
・赤紫蘇…後から追加
・漬物用の重し(梅と同じ2kg)
※ホワイトリカーではなく、食品に使えるアルコール製剤を使って容器や梅を消毒しました。
梅干し作りの流れ(私の場合)
1.梅の下ごしらえ
完熟梅を水でやさしく洗ってヘタを取り、水分を丁寧に、かつしっかり拭き取りました。 ※完熟梅の場合はアク抜きのための水に浸ける工程は不要です。 キズがつくとカビの原因になるため、やさしく扱い、水気も残さないように注意しました。

2. 消毒&塩漬け
保存容器、重し、梅はすべてアルコール製剤でしっかり消毒。 梅と塩(今回は15%)を交互に重ね、表面にも塩をふって、最後に重しをのせます。 梅と同じ重さの重し(2kg)を使って、梅酢がしっかり上がるのを待ちました。

※塩分15%は、昔ながらの梅干しに比べるとやや控えめですが、それでもけっこうしょっぱい仕上がりになります。そのぶん保存性も高く、カビも出にくいため、初心者でも失敗しにくい安心の塩加減です。
3. 赤しそ投入
梅酢が上がってきたら、塩でもんでアクを抜いた赤しそを加えます。 このときも赤しそや手に触れる器具はしっかり消毒しておきました。
赤しそは、時期によっては店頭に並ばないこともあるため、早めに梅干し作りをスタートしてタイミングを逃さないようにしましょう。 ちなみに私は、種から赤しそを育てました! 赤しそなしで作る白梅干しという選択肢もありますが、赤しそを入れると風味がぐっとよくなります。

土用干しの方法(私が教わったやり方)
今回は、和歌山県の梅づくりの達人に教えてもらった方法で干しました!
▼ 4日間の昼干し
梅をザルや網に並べて、朝から夕方まで天日干しします。
夕方には毎日取り込んで、赤しそと一緒に瓶に戻し、再び漬け込みます。
これを4日間繰り返します。
▼ 5日目の夜干しがポイント!
5日目は、朝に干した梅をそのまま夜も外に置いておき、夜露にあてます。
この“夜干し”をすることで、梅の実がふっくら柔らかく仕上がるそうです。
「夜露にあてる」なんて、初めて知った時は驚きましたが、 こういう丁寧な手間が、美味しさの秘訣なんだなあと実感しました。

初心者でもできた!気づきとポイント
・一番の敵は「カビ」!でも消毒さえしっかりすれば意外と大丈夫。
・塩分15%はやや控えめだけど、梅酢がしっかり上がればカビにくかった。
・干すときの手間も楽しくて、梅干し作りがどんどん好きになる!
梅干しのある暮らし、いいですよ
できあがった梅干しを、おにぎりや冷やし茶漬けに使うのが楽しみ! 自分で漬けたと思うと、味わいもひとしおです。
来年は塩分控えめやはちみつ漬けにも挑戦してみたいなと思っています。
まとめ
「梅干し作りって難しそう…」と思っていたけど、 やってみたらすごく奥が深くて、楽しい体験でした。 この記事が、これから梅干し作りをしてみたい方の参考になれば嬉しいです!