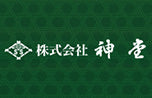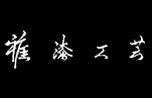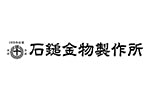夏の陽射しにきらめくガラスの器に、つるりと光る「ところてん」。
一口すれば涼風が駆け抜けるようで、昔ながらの日本の夏を思い出させます。関東では酢醤油にからしを添えてさっぱりと、関西では黒蜜をかけて甘味として楽しむなど、地域ごとに異なる顔を持つのも魅力。さらに「一本箸で味わう」演出など、文化的な広がりもまたこの食べ物を特別な存在にしています。
ところてんの歴史

ところてんの起源は中国から伝わり、奈良〜平安時代に日本で食べられていました。漢字では「心太」と書きますが、なぜ「ところてん」と読むのでしょうか。もとは海藻が煮て溶け固まる様子を「凝る藻葉(こごるもは)」と呼び、それが「こころぶと」となり、この時に「心太」という漢字が当てられました。その後、呼び方だけが変わって「ところてん」となり、漢字だけが残ったといわれています。江戸時代には庶民の屋台グルメとして定着し、浮世絵などの資料を見ると当時は二本箸で食べるのが一般的。後に観光地などで「一本箸で食べるスタイル」が演出として登場し、特別な食べ方として広まりました。
関東と関西の食べ方
 写真:(左)関西風 (右)関東風
写真:(左)関西風 (右)関東風
・関東(江戸):酢醤油にからしを添えて、軽食・肴として。
・関西(上方):黒蜜やきなこをかけて、和菓子の一種として。
同じ食材でも文化の違いで「おかず」にも「おやつ」にもなるところが面白い点です。
ところてんと寒天
ところてんを語るなら、忘れてはいけないのが「寒天」。
江戸時代、冬の京都で偶然にところてんが凍り乾燥し、それが寒天の始まりになったとも伝承されています。水分が抜けて保存性が高まり、後に棒寒天や粉寒天として全国に広がりました。羊羹やあんみつなど和菓子の世界を支えたのは、この“ところてんの変身”だったのです。
実際に作ってみたレシピ
材料(約4人分)
・天草(てんぐさ):15g
・水:1L
・酢:大さじ1
作り方
1.天草をさっと洗い、ゴミや砂を落とす。

2.鍋に水と天草を入れて火にかけ、沸騰してから酢を加える。

3.弱火で30〜40分ほど煮て、海藻の成分をじっくり煮出す。
4.ザルにキッチンペーパーを敷いて煮汁を濾す。

5.濾した煮汁を容器に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

6.固まったら「てんつき(突き出し器)」で押し出して完成。

まとめ
江戸の町で汗をぬぐいながらすする酢醤油の一椀。
京の甘味処に並ぶ黒蜜の涼味。
観光地で人々を楽しませた一本箸の演出。
そして静かに姿を変えて広がった寒天文化。
今では少し遠い存在になったところてんですが、物語を知ると不思議と食べたくなる——そんな魅力があります。自分で煮出して作れば、ただの涼味が、ぐっと歴史のある一品に変わりますよ。