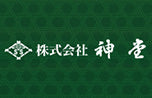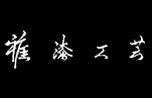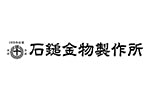料理をする際、欠かせないアイテムのひとつが「まな板」。
その中でも木のまな板は、温かみがあり、使い込むほどに味が出てきます。
今回は、木のまな板の種類や使い方、お手入れ方法などについて紹介します!
木のまな板のメリット・デメリット
まずは、木のまな板のメリットについて説明します。
【木のまな板のメリット】
・刃の当たりが良く、包丁の切れ味が落ちにくい
・手に負担があまりかからない
ほかにもありますが、この2つが大きなメリットであり、
私が木のまな板を使う理由でもあります。
また、どの素材のまな板も、長く使っていると少しずつ表面が削れてきます。
中でもプラスチック製のまな板は、
削れた部分が気になる方も多いかもしれません。
マイクロプラスチックが気になるという方には、
自然素材の木のまな板がおすすめです。
【木のまな板のデメリット】
・カビ生えやすい
・急激な乾燥に弱く、まな板が反ったり割れたりすることがある
正直、木のまな板は、お手入れや保管に少し手間がかかる部分もあります。
お手入れを怠るとデメリットで挙げたことが起きてしまいます。。。
それでも!使い続けるうちに手になじみ、
道具としての良さを実感できる素材でもあります。
丁寧に使うことで長く付き合えるのも、
木のまな板ならではの魅力であると思います。
ここからは、木の種類や手入れの方法をご紹介します。
木のまな板についてもっと知りたい!と思った人は
ぜひ見てみてください♪
木のまな板の種類
木のまな板には、いくつか種類があり、それぞれに特徴があります。
まず、知っておきたいのが「柾目(まさめ)」と「板目(いため)」の違いです。

・柾目(まさめ)
木の年輪に対して直角に繊維が走っていて、滑らかな質感が特徴です。包丁にも優しく、割れにくいため、長く使いたい方にはぴったり。
・板目(いため)
木の年輪に沿った方向に繊維が走り、見た目が美しいのが特徴です。使ううちに風合いが増しますが、柾目に比べると反りやすく割れやすいので、注意が必要です。
これを踏まえて、次は人気の木材について見ていきましょう。
人気の木材とおすすめしたい木の種類
木のまな板に使われている木材には、
ヒバ、イチョウ、ヒノキ、ヤナギなどさまざまなものがあり、
種類が多くてどれを選んだらいいか悩む人もいるのではないでしょうか?
もちろん、それぞれの種類の良さはありますが、
もし初めて木のまな板を購入するなら、
私はヒノキとスプルスのまな板をおすすめします!
理由は、値段が比較的安く、また軽くて扱いやすいかなと思うからです。
木の種類によっては高級なものがある木のまな板。
また、柾目のものは板目よりも長持ちするため価格が高くなりがちです。
しかし、ヒノキやスプルスは柾目のものでも安価で手に入りやすいので、
最初に購入するならこれらをおすすめします!
ちなみに、私が使っているのもスプルスのまな板です。
個人的には、木の独特の匂いも強くなく使い勝手がいいなと感じます😊
木のまな板の使い方
木のまな板を使うときには、いくつかのポイントを押さえておきましょう。
少しの工夫で、まな板の寿命を延ばすことができます。
・使う前に準備をしよう
使うときは、まず水でまな板全体を濡らしましょう。
これにより、食材の匂いや汚れがつきにくくなります。
また、濡らし終わったら表面を軽くふき取っておきましょう。
・切り方に気をつける
包丁はまな板と垂直になるように構えましょう。
また、包丁を押しつけるように使わず、
軽い力で切ることが木のまな板を傷めないコツです。
木のまな板のお手入れ方法
木のまな板を長く使うためには、
しっかりとお手入れすることが大切です。
以下のポイントを押さえて、いつまでも美しいまな板を保ちましょう。
・洗剤で洗ってOK!でも漂白剤はNG
木のまな板は洗剤を使って洗えますが、漂白剤の使用は禁物。
漂白剤の成分が木の中に成分がしみ込んでしまうため、使わないようにしましょう。消毒をしたい場合は、洗剤で洗ったあと熱湯をかけて消毒する方法をおすすめします。
・使った後はしっかり乾燥
使用後は、軽く洗って水分を拭き取り、しっかりと乾かすことが大事です。水気を放置すると、木が反ったり割れたりする原因になります。
・注意すること
木のまな板は、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管することが重要です。
また急激な乾燥に弱いので、エアコンの風が直接当たらない場所で保管しましょう。
まとめ
木のまな板は、使うほどに味わいが増し、料理をもっと楽しませてくれるアイテムです。お手入れさえしっかりすれば、長く愛用できるので、ぜひ大切に使ってくださいね!