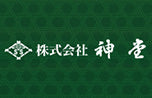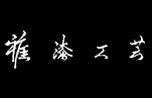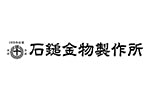This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
牛刀の一覧ページです。堺孝行や堺菊森、グレステンなど、プロ仕様の包丁ブランドを集めました。力強い切れ味と耐久性が特徴です。
From the blog
MADE IN NIIGATAの一品、「まどろむ酒器」をご紹介。
冷たいお酒を注ぐと模様が色づく、燕市発の「まどろむ酒器」。見た目の変化も楽しめる遊び心ある酒器として、自宅飲みや贈り物に人気のシリーズです。
夏の涼味「ところてん」の魅力|歴史・食べ方・レシピで楽しむ日本の伝統食文化
昔ながらの夏の涼味「ところてん」。江戸では酢醤油、関西では黒蜜と、地域ごとに異なる楽しみ方があります。本記事では心太の語源や寒天との関係、そして天草から作るレシピまで、日本の食文化をわかりやすく紹介します。
土用の丑の日にうなぎの蒲焼|関東風と関西風の違いも解説
暑さが続く夏。食欲が落ちがちなこの季節に食べたくなるスタミナ料理といえば「うなぎの蒲焼」。「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣はすっかり定着していますが、実はそのルーツや地域ごとの調理法には、奥深い歴史と文化が隠れています。今回は、自宅で本格炭火焼きが楽しめる「いろはコンロ」を使って、関西風の香ばしいうなぎの蒲焼を作ってみました。市販の蒲焼とはひと味違う、自分で焼くうなぎの魅力をお伝えします!
MADE IN NIIGATAの一品、「まどろむ酒器」をご紹介。
冷たいお酒を注ぐと模様が色づく、燕市発の「まどろむ酒器」。見た目の変化も楽しめる遊び心ある酒器として、自宅飲みや贈り物に人気のシリーズです。
夏の涼味「ところてん」の魅力|歴史・食べ方・レシピで楽しむ日本の伝統食文化
昔ながらの夏の涼味「ところてん」。江戸では酢醤油、関西では黒蜜と、地域ごとに異なる楽しみ方があります。本記事では心太の語源や寒天との関係、そして天草から作るレシピまで、日本の食文化をわかりやすく紹介します。
土用の丑の日にうなぎの蒲焼|関東風と関西風の違いも解説
暑さが続く夏。食欲が落ちがちなこの季節に食べたくなるスタミナ料理といえば「うなぎの蒲焼」。「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣はすっかり定着していますが、実はそのルーツや地域ごとの調理法には、奥深い歴史と文化が隠れています。今回は、自宅で本格炭火焼きが楽しめる「いろはコンロ」を使って、関西風の香ばしいうなぎの蒲焼を作ってみました。市販の蒲焼とはひと味違う、自分で焼くうなぎの魅力をお伝えします!